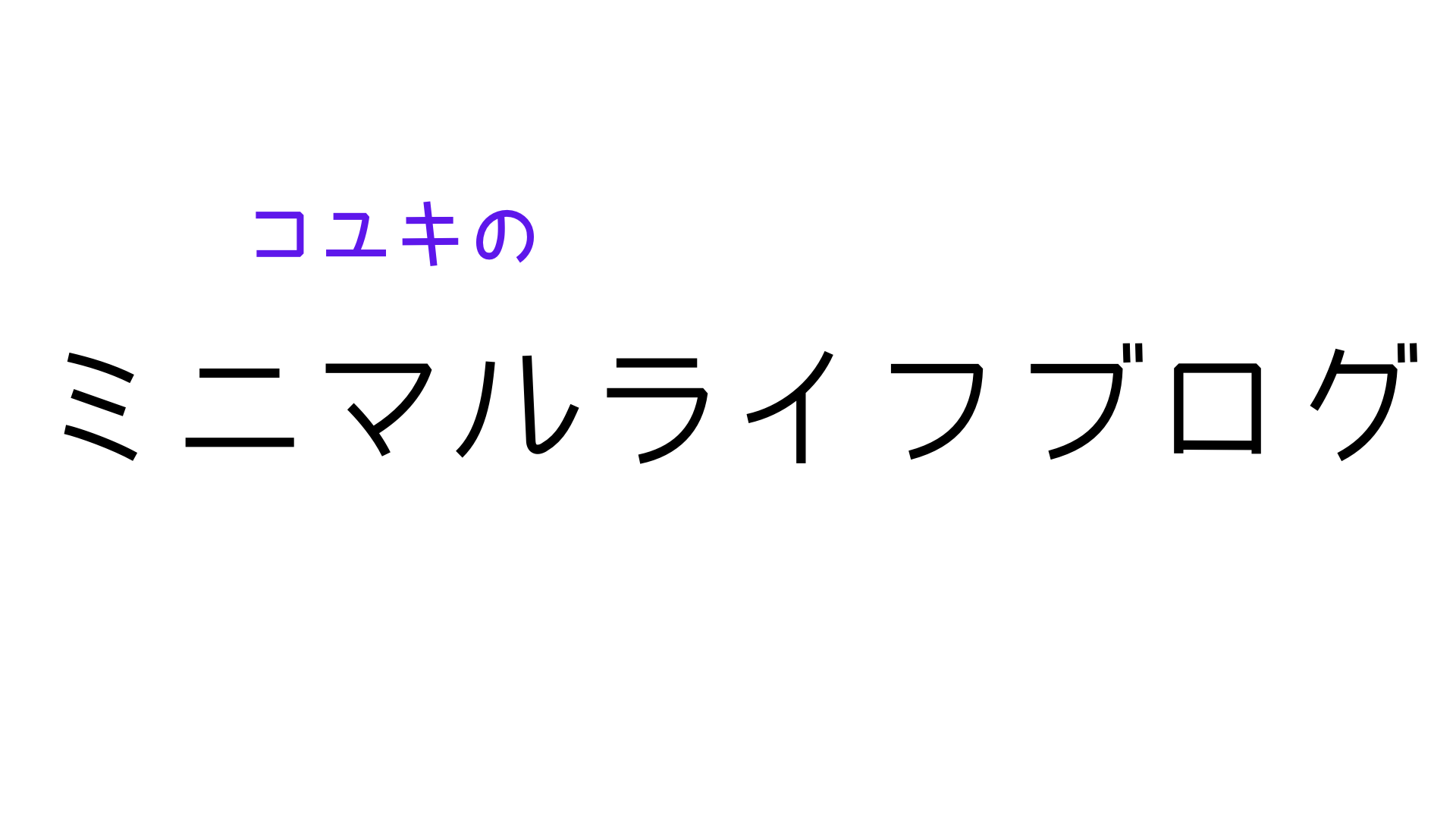6月に公開された映画「国宝」の興行収入が166億円を超えたそうです。(←10/26の数字)
いまさら感はあるけれど、感想かきます。といってもネタバレ的なストーリーについての感想ではありません。私がこの映画の魅力についてあれこれ考えたことの備忘録です。
私が観たのは7月初旬。結構前だけど、観てから原作読んだり色々調べたり考えてたら10月になっちゃった(笑)

はじめに。私は歌舞伎ファン歴30年以上です。日本舞踊も師範資格を持ってる。かなりどっぷりと歌舞伎や伝統芸能の世界の人たちとの交流なども過去たくさんあったので、この世界の裏も表も結構知っていて。こんな経歴があるのでこの映画を純粋には楽しめなかったかもしれない。どうしても比較したり考えたりしてしまってし、物語に没入しきれなかったなぁと。
でも私が観終わってまず思ったのは、喜久雄役の吉沢亮さんと俊介役の横浜流星さんのふたりのキャスティングなしにこの映画のヒットはなかったのだろうな〜ということでした。これは絶対不可欠だったと思う。
「国宝」の監督を務めた李相日さんは、主役は最初から吉沢亮だと決めていたらしい。彼が主役の喜久雄を演じるなら、小説「国宝」の映画化は可能になる、と。つまり監督の思惑は予想的中だったわけです。
容姿の美しさ、華のあるオーラ。現在20代の俳優の中でもふたりは群を抜いてると思うし、そのうえ芝居への取り組む姿勢は尋常なほど真摯。画面から溢れるのは「本気度」マックスの、役者魂。歌舞伎役者としての生涯をなんとも切なく美しく描くことができたのは、ふたりの存在あってこそ。
そして私的視点でいえば、やはり歌舞伎役者としての立ち居振る舞いが、予想していた何倍も素晴らしかったという点は外せません。
二人はたった1年半のお稽古期間で撮影に入ったとか。メディアでは「1年半も練習した」と準備に長期間をあてたことに驚嘆の賛辞を送っているけれど、私からすると「え。たった1年半!?」って感じ。日本舞踊って本当に難しいし、まして大人になってから習うと更にハードルは高い。普通、1年半じゃお遊戯レベルしか無理。
日本舞踊の難しさを伝えるとしたら。。たとえば「三つ振り三年」という言葉があります。三つ振りとは日舞のごく単純な決めポーズで、この動きをちゃんと習得するにも最低3年はかかるよ、という意味で。他の初歩・基礎的な動きも同じく3年は普通かかる。それに歩くといっても役柄によって歩き方が全然変わる。女形なら左右の内腿をくっつけたまま歩く。紙を一枚挟んでそれを落とさないように歩くイメージです。そして肩甲骨はぐっと寄せて脇は力を入れてしめ、でも肩の力は抜く。実際やってみてたらわかると思うけど、これめちゃしんどい。まして男性がやるならなおのこときつい。
横浜流星はなで肩なので女方の肩の使い方が上手にできてました。でも吉沢亮は肩がっしりしてるから、女方の仕草に苦労なさったと推測。私もいかり肩なので女役で踊る時の肩の使い方にはとても苦労しましたから。
で、私が言いたいのは、吉沢亮と横浜流星はたった1年半のお稽古で大演目「娘道成寺」や「曽根崎心中」やらを映画の中でやりきったのは、本当に奇跡レベルですごい!ということ。
踊りのシーンがそれなりに歌舞伎役者っぽくみせてることに驚愕したし、ちょっとすごくて笑ってしまったくらい!もちろん所作にアラはあったけど、予想の何倍も立派に踊ってたし、歌舞伎に詳しくない人なら歌舞伎役者と信じ込ませられるな〜と思った。とにかくあのレベルは1年半では普通は無理です。真似できるとしたら「ガラスの仮面」の北島マヤだけ(笑)
ただふたりには多少なりの素養はあったかも。調べてみたら吉沢亮は小学〜高校の9年間剣道(二段)を、横浜流星も小学生の時から極真空手(初段)をやっていたそうな。流星くんは2011第7回国際青少年空手道選手権大会13・14歳男子55kgの部で優勝し、世界一にもなったことがあるらしい。
剣道も空手も腰を落としてすり足、というのは基本の基本。他にも足捌きや構えなどで共通することはたくさんある。それに丹田に重心がある動き、というかそれも共通する。芯がぶれないという感覚をふたりの体は無意識に知っていたはず。だからなおのこと「歌舞伎役者らしく」みえたのかも。それはこの映画だけでなく、普段からお二人の映画俳優としての立ち居振る舞いを美しいものにしている元となってるということも。
この映画に出演されてる寺島しのぶさんが、SNSで「国宝」のことでこんなことをおっしゃっていて。
”前、某監督が、映画だったら作り物だから何やってもいいし、そこに自分の思いを載せられる。警察だって劇中だったら殺せるからねって言っていたことを思い出した。”
この発言、ああなるほど、と。
本物の歌舞伎役者になる必要はない。映画の中でだけ「この人は歌舞伎役者」と観客に信じ込ませられたらいい。
映画とは虚構の世界、嘘の世界。嘘の家族、嘘の恋人たち、その人たちが上映時間の中で泣いたり笑ったりしてる。映画とはそういうモノ。ゆえに矛盾もいっぱいおこる。制限ある時間の中での物語の進行には矛盾はつきもの。私の主観だけど、矛盾を、矛盾と感じさせすに観終えた映画に傑作作品は多い。「国宝」もまた、それに該当する映画だったということです。
さらに没入感を高めたのは、独特な撮影にも仕掛けが。特に歌舞伎の舞台でのシーンは俳優の表情にかなり接近して撮っている。観てる時は私はこれが不自然に感じたのだけど、実はこの撮影アングルが、歌舞伎をより歌舞伎らしくみせたのではないか、って思って。
というのも、歌舞伎は通常舞台だから観客は全体を引きで観ている。でもこの映画で舞台のシーンを全体に映してしまえば、「嘘」であることがバレてしまう。ふたりには「型」がまだ叩き込まれていないから。でも目の動きや微細な表情の変化をアップにすることで歌舞伎の型そのものよりも、心情に迫っていき、偽物だとバレることはない。
撮影したのはチュニジア出身のソフィアン・エル・ファニ。2014年にフランス映画「アデル、ブルーは熱い色」でカンヌ国際映画祭のパルム・ドール賞をはじめ多くの映画賞を受賞した作品の撮影を担当していて、私もこの映画を観たことあるけど、とても素晴らしい映画で。(のちに賛否の論争がおきたシーンは私も否定的ですが)やはりとても接近して撮っているシーンが多いのだけど、表情に迫ることによる効果なのか、物語が進むに連れて不思議と映画の人物と一体化していった。
李監督はこのエル・ファニについて、あるインタビューでこう話している。
彼が撮影監督を務めた『アデル、ブルーは熱い色』(2013 / アブデラティフ・ケシシュ監督)という作品、あれは全編、手持ちカメラで撮影しているんです。3時間くらいの長編作品で、本当に生々しく芝居を撮っています。『国宝』は全編ということはないんですが、ここぞという時には手持ちカメラです。つまり、歌舞伎を撮っているようでいながら演じる者の心のうちを撮ろうという、そういうタイミングですね。それはソフィアンの手持ちカメラでの撮影のセンスが、最も生きた瞬間だったと思います。
李監督がこの人を撮影監督にしたことも、大きな勝因だと思う。采配がとにかくうまい。
あ、でも私は渡辺謙さんはちょっとミスキャストじゃないかな〜と思った。渡辺謙さんはとても大好きな俳優さんですが、あの方は主役で映える人というか。強いから脇だと少ししんどい。
で、原作は小説を読もうかと思ったのですが、オーディブルで尾上菊之助さん(録音当時の名前です)が読みきかせてるのを知って、これは絶対オーディブルがいい!となり、聴いたのですが、これがめちゃくちゃ良かった〜
まずさすが菊之助さん、登場人物によって方言、口調、トーンを見事に変えていく。そして当たり前だけど歌舞伎のセリフのシーンが素敵過ぎる。原作読んだ人もそうでない人も、これ、めちゃおすすめ!尾上菊之助の崇高な芸を聴いてみてほしい〜。
聴き応えがあるので何度か噛み砕いてまた聴いてみたくなる作品だと思いました。やはり本も買って読むかもって思ったくらい、面白かった。
最後に。私も過去歌舞伎の人間国宝の方の芝居は何度も拝見している。片岡仁左衛門さん、坂東玉三郎さん、7代目の尾上菊五郎さん。心に残る芝居がいくつもある。
故・2代目中村吉右衛門の至芸には何度も唸った。勧進帳は私の大好きな演目でたくさんの役者の方の勧進帳を観てきたけど、吉右衛門さんの弁慶が一番好きだった。熊谷陣屋の最後の名シーンでいうセリフ「十六年は一昔、ァゝ夢だ、夢だ」となげく場面、いまでも思い出すだけで涙が出てくる。
そしてなんといってもこの「国宝」で田中泯さんが演じた小野川万菊のモデルとも噂されている、故・6代目中村歌右衛門は、この世の人ではないと思った唯一の方。私が観た頃、もうかなりご高齢で声も体も小さくて、正直何言ってるのかわからなかったけど、存在感は途方も無いスケールだった。歌右衛門さんが舞台に登場すると、客席は張り詰めた空気になる。あの圧倒的オーラと、支配力は誰にも真似できない。まさに化け物。
そんなことを考えながら。配信になったらもう一度観てみたい。